| 契約書 |
|---|
|
最初に.札幌で友人にお金を貸してと頼まれたら 最初に.札幌で売買契約をするなら 最初に.札幌で合意・示談(和解)できるなら 最初に.札幌で結婚をするなら 最初に.札幌で賃貸借契約をするなら 最初に.札幌で贈与契約をするなら A.契約書とは B.契約書作成の意義 C.契約自由の原則と例外 D.業務/契約書作成の種類 E.業務/契約書の作成にかかわる相談 F.業務/通常の契約書と公正証書(協議済) |
|
A.契約書とは タイトルに「○○契約書」とある場合だけが契約書と思われている方もおられますが、「合意書」「示談書」「協議書」「協定書」 等と書かれていても、同じく「契約書」なのです。 ですから、契約書とは大変に幅広い使い方をされる書類なのです。 |
|
B.契約書作成の意義 法令で書面が必要とされている場合に契約書を作成することは当然ですが、それ以外の場合でも、 当事者間で協議がまとまれば、口約束という言った言わなかったの水かけ論を防止する手段として重要な証拠書類となる『契約書』を作成することは、大切な事です。 (書面の有無による契約解除の違い:例1)贈与契約の場合 改正民法第550条(施行日:2020年4月1日) 第1項「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」 ☆もらう側から見ると口頭契約と比べ書面契約の方にメリットが発生する場合があります。 (書面の有無による契約解除の違い:例2)消費貸借契約の場合 改正民法第587条の2(施行日:2020年4月1日) 第1項「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」 第2項「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」 第3項「書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」 第4項「消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」 (書面の有無による契約解除の違い:例3)使用貸借契約の場合 改正民法第593条の2(施行日:2020年4月1日) 第1項「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。」 (書面の有無による契約解除の違い:例4)寄託契約の場合 改正民法第657条の2(施行日:2020年4月1日) 第1項「寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。」 第2項「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。」 第3項「受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。」 |
C.契約自由の原則と例外
|
D.契約書作成の種類
|
|
E.業務/契約書の作成にかかわる相談 各種契約書作成に関し必要な法務相談を致します。 |
|
F.業務/通常の契約書と公正証書(協議済) 普段生活をしている上で、よく見かける契約書は、ほとんどが「通常の契約書」でしょう。 又、「公正証書」作成の場合、公証人手数料がかかってしまうデメリットがあるとはいえ、 契約内容に金銭の支払いがある場合等は、債権者側にメリットがあります。さらに、「通常の契約書」ではなくて、 「公正証書」である必要がある契約書もあるのです。 契約書作成のご依頼では、最初に、当職とご依頼者様との打合せにより、ご依頼者様のご希望をもとに当職が整理して原案を作成いたします。ご依頼者様に確認いただき問題がなければ、正式な契約書を作成いたします。 「通常の契約書」または「公正証書」どちらで作成する場合も当事務所へご依頼下さい。 |
|
<注意事項> 行政書士は、本人に代わって代理交渉をすることが出来ません。 ですから代理交渉が必要な場合、又は既に当事者間で争いになっている場合は、業務範囲外となります。 ※裁判所に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士の専管業務です。 (参考:弁護士法第72条) ご依頼された業務から、発生した他士業の業務は、必要に応じて当事務所から 他士業者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士等)を紹介致します。 |
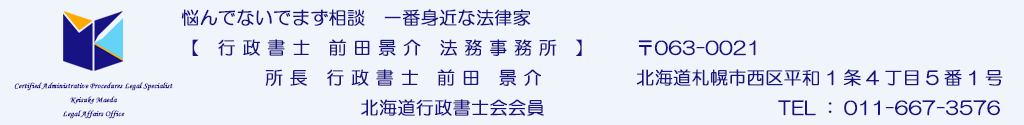
|
| Copyright © 2005-2026 Certified Administrative Procedures Legal Specialist Keisuke Maeda Legal Affairs Office. All rights reserved. |